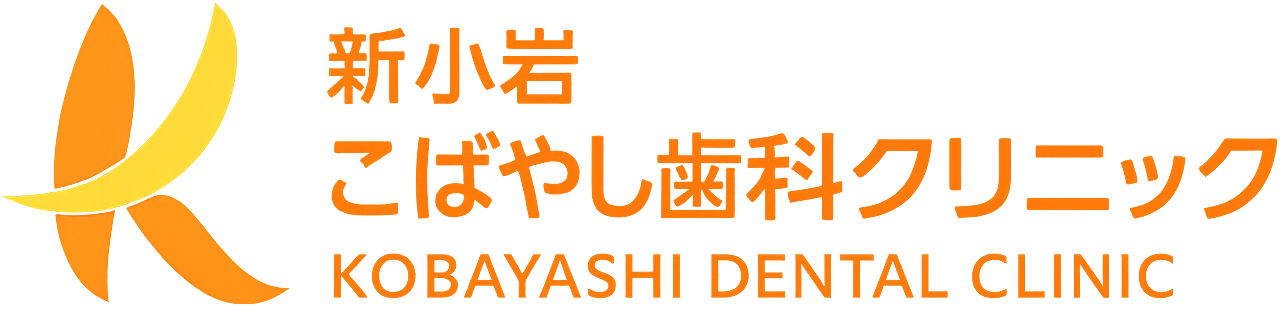今回は知覚過敏についてお話したいと思います。知覚過敏は経験された方が多いのではないでしょうか。
知覚過敏とは?
知覚過敏とは、歯ブラシの毛先が触れた際や冷たい飲食物・甘いもの・風があたった時などに歯に感じる「キーン」とした一過性の痛みです。
むし歯や歯の神経の炎症などの病変がない場合にみられる症状です。
知覚過敏になる原因

知覚過敏の原因として考えられることは、歯周病や加齢などにより、歯の根元の部分の象牙質が露出してしまうことです。
健常な歯では象牙質はエナメル質と歯肉におおわれていて、冷たさなどの刺激から守られています。
しかしながら、歯周病が進行したり、加齢や不適切なブラッシング、不正な咬み合わせ、歯ぎしり(咬合性外傷)などで歯茎が下がってしまうと、歯の根元の部分の象牙質が露出してしまいます。
象牙質には神経につながる無数の穴(象牙細管)があるため、この穴を通して、受けた刺激が神経に伝わり痛みとして感じてしまうのです。
知覚過敏を防ぐには?
知覚過敏にならないようにするには、適切なブラッシングで歯の象牙質の露出を防ぐことが大切です。
知覚過敏は鋭い痛みのため、ブラッシングを嫌がってしまう場合もあり、結果、歯垢が蓄積してしまいます。
蓄積した歯垢は細菌がたくさんいます。その菌達が産生する酸によって、露出した象牙細管がさらに広がってしまい、刺激を感じやすくなり痛みが憎悪してしまいます。
また、ブラッシングの励行をしないことで虫歯や歯周病の発症、悪化といった悪循環を繰り返してしまいます。
知覚過敏を事前に防ぐ具体的対策
知覚過敏の予防としてのブラッシングは以下のような方法があります。
- 毛先を歯にきちんと当てる。
- 磨く際の力は軽く。
※歯をみがく力が強すぎると歯ブラシの毛先が開き、動きが止まってしまうため、プラーク(歯垢)が落ちにくくなります。また、歯の摩耗の原因にもなります。 - 歯ブラシは小刻みに動かして使う。
- やわらかめの毛の歯ブラシを使う(特に歯肉炎や歯周炎の方)。
- 歯がしみる時には、冷水ですすがず、ぬるま湯を使用する。
知覚過敏への対応としては、現在では歯磨き粉による個人的な対応が多いでしょう。
知覚過敏用歯磨き粉には、硝酸カリウムという刺激の伝達を防ぐ薬用成分が入っています。
また、刺激が伝達する象牙細管の入り口をふさぐ薬用成分として、乳酸アルミニウムというものが配合されています。
これらにより歯が「しみる」のを防ぎます。
この症状は歯科医に相談しましょう

くさび状欠損といい、歯の歯頚部が欠けている場合があります。この状態は歯磨き粉では治りませんので、歯科医院にて治療を受けましょう。
以上が知覚過敏のお話でした。
口腔内で何か気になるようなことがある場合はいつでもご相談ください。